[2]私を捕らえる彼の瞳
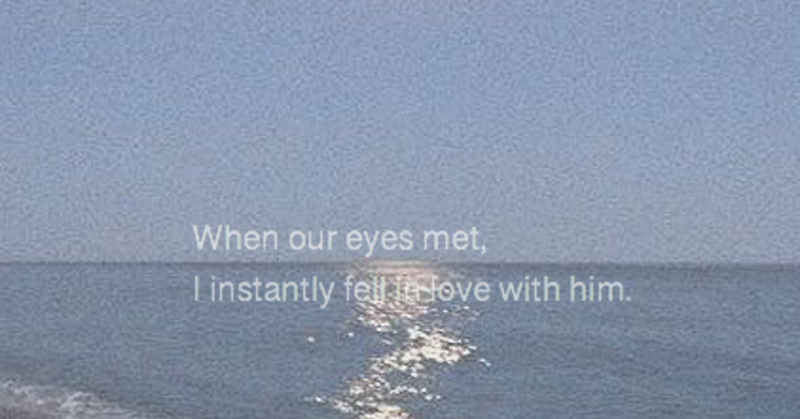
彼の瞳に見つめられると息が止まるような感覚になった。色素の薄い瞳は彼の性格がそのまま現れたような優しさと慈愛に満ちたかがやきを持っていた。その瞳がキラキラとするのはいつもふたりで行った伊豆でサーフィンをしていたが一番だと思う。子どもみたいな無邪気な笑顔で海へ入る彼のかっこよさは多分、世界で一番だと今でも思うよ。
太陽が反射して宝石みたいに波がきらめく。毎回、上手く波に乗れない私に怒るわけでも呆れるわけでもなくあっけらかんと笑う少し低めの声や長い睫毛についた水滴、どんな波でも簡単に乗りこなす軽やかな体、彼のお気に入りのカラーのサーフボード。くたくたになるまで波に乗っている時間が幸せだった。彼にはサーフ友達もいたし私もそこで仲良くさせてもらって、夜はみんなでよくビーチ沿いで波の音を聞きながらカクテルを飲んで潰れるまで歌ったり踊ったりしてた。
お酒が入ってほんのりと赤みを帯び、アルコールに弱い彼は殆どふんわりとしているのに、時々、真剣な眼差しで漆黒に染まった海を眺めていたあの横顔は今となってはどんな事を考えいたのか知ることも出来ないのだけれど、いつも優しい雰囲気からは想像もできないくらい辛い事や死んじゃいたくなる苦痛を乗り越えてきた人の持つ、パワーみたいなものを感じていた。あの時に聞けばよかった。彼の心の奥まで触れたかった。それでも踏み込まれたくないのかなと踏み込めなかった。本当は踏み込んで私の知らない彼を知るのが怖かったのかもしれない。そんな私に気がついていたのか、私の視線に気がつくと、大きくて暖かな手を伸ばしてひとしきり頭を撫でた後に引き寄せてくれて彼のブランケットに一緒に包んでくれた。彼の腕の中にすっぽりと収まる頃には彼の瞳はいつものきれいな淡い光を放つ優しい笑顔に戻っていた。
いつまでたっても私は彼の瞳に見つめられると吸い込まれそうで、ずっとずっと見ていたいのにドキドキしてしまって上手く見れなかった。もっともっと見ておけばよかった。焼きつくくらい見ておけば良かった。彼の瞳に捕らわれていたかった。もうあの瞳が見つめるのは私じゃない事がひどく悲しかった。私が見つめるのも彼じゃなくなる日はくるのかな…。
いまだって夢に出てきてくれるくらいだから、きっとしばらくは無理なんだろうな。
街の中で、電車で、誰かとすれ違う時に無意識にあの瞳を探してしまう。
改めてまだまだ私は彼が好きで仕方がないみたいで、今日も夢の中でいいからあの瞳に捕らわれていたいと願う。

